こんにちは。加藤隆佑です。
本日は、長生きするための方法について解説したいと思います。
長生きする方法には2つの考え方がある
① 時間的に長く生きること
これは、単純に「寿命を延ばす」という考え方です。
例えば、100日生きるより200日生きる方が、時間的には長生きしたことになります。
がんの方が病院での治療を受けることによっても、そのような効果が期待できます。
② 体感的な時間を長くすること
こちらは、「人生の充実度を高める」という考え方です。
同じ1日でも、過ごし方によって長く感じたり、あっという間に過ぎたりすることがあります。
例えば、旅行に行くと、わずか2日間でも印象深い思い出になり、まるで何十日分もの経験をしたように感じることがあります。
さらに、10年後になっても、その旅行の記憶が鮮明に蘇ることもあるでしょう。
つまり、ただ長く生きるだけでなく、「充実した時間を増やす」ことも大切なのです。
翌日になって、昨日の出来事がそれなりに頭に残っていれば、充実した時間を過ごしていると言えるでしょう。
人生の時間は意外と短い
仮に80年の人生を送るとしても、実際に意識的に使える時間は思っているより少ないです。
• 1日6時間睡眠なら、人生の20年間は睡眠時間
• 1日8時間睡眠なら、人生の27年間は睡眠時間
そう考えると、自由に使える時間は 53年から60年程度 しかありません。
その限られた時間を、できるだけ「体感的に長く感じるように」過ごすことが大事になります。
これは、単に忙しくするという意味ではなく、充実した時間を増やすということです。
充実した時間とは?
「無駄な時間=悪いもの」と考える方もいるかもしれませんが、決してそうではありません。
例えば、友人との何気ない雑談も、楽しかった思い出として心に残り、安心感や幸せを感じられる時間になります。
そういう時間を増やすことが大切です。
スマホ・タブレットの使い方を考える
しかし、最近ではスマホやタブレットの普及により、人と直接話す時間が減り、スマホを見て過ごす時間が増えています。
例えば、1日3時間スマホを使うとします。
これを20年間続けると、スマホに費やす時間は 2.5年分 にもなります。
もちろん、仕事でスマホを使うことは問題ありません。しかし、仕事以外の時間もスマホを見ている方は多いのではないでしょうか?
ここで、ひとつ考えてみてください。
「昨日スマホを3時間使ったとして、その時間に見たものをどれだけ覚えていますか?」
おそらく、ほとんど覚えていないのではないでしょうか。
これは、「スマホに費やした時間は、記憶にも残らず、人生の充実度を上げていない」ことを意味します。
スマホの影響は意外と大きい
さらに、脳科学的にもスマホの使いすぎには問題があると言われています。
• 子供の脳の発達に悪影響を及ぼす
1日3時間以上スマホを使った子供の脳をMRIで調べたところ、本来発達するべき領域が発達していなかったという報告があります。
• 認知症のリスクが上がる
スマホの長時間使用が、記憶力や思考力の低下につながる可能性が指摘されています。
スマホは便利なツールですが、無意識に使いすぎると
「健康的なリスクの上昇」並びに、「気づかないうちに人生の大切な時間を奪われている」 かもしれません。
人生をより充実させるために
「寿命を延ばすこと」には限界がありますが、「体感的な時間を長くすること」は自分の工夫次第で可能です。
そのために、次のような時間を意識的に増やしてみるとよいでしょう。
• 人との交流・会話(直接話すことで、心に残る時間が増える)
• 旅行や新しい体験(記憶に残り、時間の密度が高まる)
逆に、翌日の記憶にほとんど残らないような 「なんとなくスマホを眺める時間」 を減らすことも大切です。
人生は有限です。どうせ同じ時間を過ごすなら、できるだけ「長く感じられる」時間を増やしていきませんか?
具体的にすべきこと
スマホに費やす時間を減らすことが、充実した人生に繋がり、さらには、脳への悪影響を減らし、将来的な認知症のリスクを減らすことができると私は考えています。
私が実行していることの1つは
スマホやタブレットを使うのは、スマホやタブレットでしかできないことをするときだけにすることです。
具体的には、
・スマホやタブレットは、自分の近くに置かないようにしています。
・パソコンで代用できることは、パソコンでします。目覚まし時計も、スマホは使わず時計を使います。
・Kindleといった電子書籍も読まないようにして、紙媒体のものを読みます。
昭和大学の研究チームが行った調査によると、紙の本の方がスマートフォンよりも内容を記憶しやすく、読解力が高まるという結果が得られているからです。
この研究では、以下のような興味深い発見がありました:
読解力テスト:
紙の本で読んだ場合:平均8.9点
スマートフォンで読んだ場合:平均7.4点
深い呼吸(ため息)の回数:
紙の本:平均3.3回
スマートフォン:平均1.8回
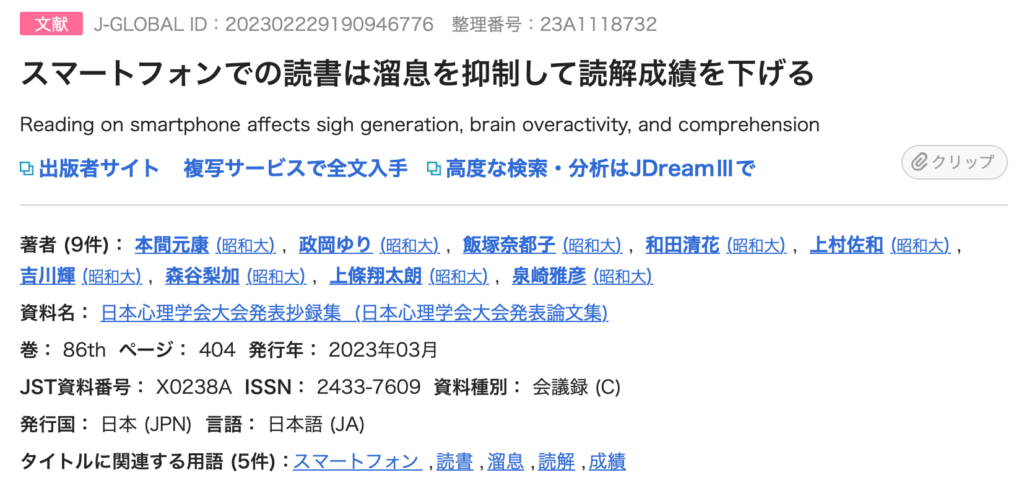
以上のようにして、スマホやタブレットを使うのを最低限にします。
電磁場の影響を下げるためにどうする?
年々電磁波を使う量が年々増えており、それによる体へのダメージは未知数です。
ただ、以下のようなデータもあります。
1、人間のIQが次第に低下しているというデータが複数の研究で報告
・IQの低下傾向
ノルウェーの研究チームが行った大規模な調査によると、1975年以降、IQスコアの平均が世代ごとに低下していることが明らかになる。
1962年から1975年生まれの対象者では、IQスコアの上昇が見られた一方で、1975年以降生まれの対象者では、1世代あたり平均7ポイントのIQスコア低下が確認された
他国での同様の傾向もあり、この現象はノルウェーに限らず、他の欧州諸国でも確認されています。
今後、IQスコアがさらに低下する恐れがあります。
2、右肩上がりで上昇している認知症のリスクがさらに上がることも懸念される。
若年性認知症の有病率は47.6人から50.9人へとわずかに増加してきています。
これがさらに上昇する可能性があります。
このような問題の原因として、電磁場が関与している可能性は十分にあり得ます。
そして、日常生活で頻用しているスマホ・タブレットが、電磁場の影響を大きく与えるデバイスの1つである可能性は否めません。
スマホやタブレットそのものがリスクとなるのは、スマホやタブレット自体が発する電磁場の方が、一般的な環境中を飛び交う電磁場よりも強いからです。以下のような特徴があります。
・スマートフォンは電磁波を発生させる機器であり、使用時には高周波帯の電磁波を放出。
・スマートフォンの特定の部分、特にイヤースピーカー、ラウドスピーカー、ロジックボードの周辺では、強い磁場が発生。
・スマートフォンに直接触れたり近づいたりすると、電磁波の強度が増す。これは電磁波の強度が距離に反比例して減衰する。
普段から少しでも電磁場への曝露を減らすために
・Blootooth機能は使わないときはオフ
・タブレット・スマホを使わないときは遠くに置いておき、最低限の時間だけ使うようにする。
その結果、
スマホやタブレットで、何も記憶に残らない時間を過ごさずに済むようになります。
時間の過ごし方をより有意義にしつつ、将来の脳に関連する健康のリスクを低減できる可能性もあると考えています。
実際に実行してみてほしいです。
そうすると、手持ち無沙汰な時間が増える方も多いかもしれません。
それは、自由に使える時間が増えたことを意味します。
自由な時間が増えることで、より充実した時間を過ごせるチャンスを得たことになります。
そのような時間を、新しいことにチャレンジしたりするといったことに費やす時間にしてほしいです。
